
プロローグ
こんにちは、ひまわりの陽太です。
最初に、少しこんなお話をしてみたいと思います。
多くの人は、何か新しいサービスに触れたとき、
「使いやすいね」「ここを直したらもっと便利かも」といった、
ユーザーとしての感想を持つところで止まってしまいます。
たとえば、最近のコンビニにあるセルフレジ。
「レジが早くなって助かるな」と感じる人は多いと思います。
でもそこで終わってしまうんです。
一方で、ユニクロのセルフ会計機を思い出してみてください。
何着もある服をまとめて専用ボックスに入れるだけで、
一瞬で金額が読み取られて会計ができる、あの画期的なシステムです。
「すごいなぁ、便利だなぁ」で終わるのか。
それとも「これ、コンビニにも応用できるんじゃないか?」と考えられるのか。
この“ちょっとした視点の違い”が、
実は人生やビジネスの可能性を大きく分ける分岐点になります。
でもなぜ、ほとんどの人がそこまで考えられないのか。
それは、僕たちが小さいころから受けてきた“教育”が大きく影響していると、僕は思っています。
学校では、ルールがあり、授業の流れも決まっていて、
運動会や文化祭ですら“進行表”に従って動くのが当たり前でした。
自由に考える機会なんて、そう多くはありません。
「これとこれを使って、好きなものを作ってごらん」
そんな授業、どれくらいあったでしょうか?
せいぜい、夏休みの自由研究くらいじゃないでしょうか。
そうやって育ってきた僕たちは、
気づかないうちに「正解を探すこと」が癖になっていて、
“自分で考えて何かを生み出す”ということに対して苦手意識を持ってしまっているのです。
でも、そのことに気づいている人は、案外少ないように感じます。
僕自身、進学にも失敗し、就職にもつまずき、
引きこもりになった時期もありました。
会社を作ってはみたものの、それも倒産させてしまいました。
いわゆる「どん底の人生」を、長い間過ごしました。
でも、そのどん底の中で、ようやく気づけたことがあります。
それは、僕たちが思っている以上に、
“思考”や“行動”が、過去の教育によって縛られているという事実です。
そして、そこから抜け出すための道があるということにも。
今の日本にも、僕と同じように「なんだかおかしいな」と気づいている人はたくさんいると思います。
でも、それを言葉にしたり、行動に移したりできる人は多くありません。
なぜなら、周りには「ルール通りに生きてきた人たち」しかいないからです。
自分だけ違うことをすると、浮いてしまう。叩かれる。
だからこそ、人は“気づいているのに動けない”状態のまま、
モヤモヤを抱えて日々を過ごしてしまうのです。
でも、僕は思います。
もっと自由にならないと、生きるのがしんどいだけです。
ただ苦しくて、ただ疲れて、
本当の自分を押し殺したまま生きる人生なんて、あまりにももったいない。
僕は、そんな人生から抜け出したくて、考え続けてきました。
そして、やっとの思いで見つけた「自由に生きるヒント」を、これからお話ししていきます。
結局のところ、自由とは何か。
そして、人が本当に求めているものって何だろうか。
それを僕なりにずっと追いかけてきました。
最近になって、改めて思うんです。
尾崎豊が歌っていた“自由”や“愛”こそが、答えだったんじゃないかって。
若い頃はただ何となく聴いていた言葉が、
今では「彼は現実を見た上で、それでも希望を信じていたんだな」って、
そんなふうに感じられるようになりました。
ただ反抗していたわけじゃない。
この社会の歪みや、誰にも言えない孤独や、生きづらさを、
尾崎は真正面から見て、感じて、歌っていたんですよね。
そう思えば思うほど、ますます彼のことを尊敬するようになりましたし、
ファンでいることに誇りを持てるようになりました。
あなたももし、日々の中で少しでも“モヤモヤ”や“生きづらさ”を感じているのなら、
この「自由」や「愛」という言葉を、もう一度考えてみませんか?
きっとその中に、あなたなりの答えが見つかると思います。
これから数章にわたって、
僕自身がどん底から自由を手にしていく中で見えてきた、
いくつかの“気づき”をお話ししていきたいと思います。
第1章では、そのはじまりとなる「学校教育」というテーマから掘り下げていきます。
なぜ僕たちは、“自由に考えること”が苦手になってしまったのか。
そして、どうすればその枠から抜け出すことができるのか──。
少しずつ、自分自身の内側と向き合いながら、
本来の「自由な生き方」を取り戻す旅を、ここから一緒に始めましょう。
第1章:学校という名の思考停止工場
「正解を探すクセ」はどこで植え付けられたのか?
小学校に入ったあの日から、僕たちの頭の中には“あるクセ”が染み込んでいきました。
それは「正解を探す」というクセです。
テストでは、決められた答えを選ばなければ×がつきます。
授業中に手を挙げて発言するのも、先生が望む“模範解答”が求められます。
間違った答えを言えば、クスクス…と笑われることもありました。
そんな経験を繰り返すうちに、僕たちはいつの間にか「正しい答えを探すことが大事なんだ」と思い込んでしまいます。
自分の考えよりも、正解かどうかが重要になる。
その結果、自由な発想や、自分の感覚を信じることが、どんどん苦手になっていくんです。
自由に考えていいよ、って言われた記憶ありますか?
ちょっと思い出してみてください。
「自分で考えていいよ」「好きにやっていいよ」と言われた記憶、ありますか?
図工や音楽の授業でも、「この通りに描こう」「このように演奏しよう」と、
どこかに“お手本”がありましたよね。
自由に見える授業でさえ、実は見えない枠の中にいたんです。
唯一、自由を与えられたように感じたのは、夏休みの「自由研究」。
でも、それさえも提出して“評価”されました。
つまり、「自由にやってごらん」と言いながらも、
最終的には“ちゃんとした形”を求められていたんです。
自由なようで、不自由──なんだか矛盾してますよね。
周囲に合わせて“浮かないようにする”訓練
それに加えて、学校ではこんな空気もありました。
「周りに合わせることが大事」「空気を読めないと面倒なことになる」
発言しすぎる子は「うるさい」と言われ、
ちょっと変わったアイデアを出すと、「え、なにそれ」と笑われたり…。
僕も、小学校の時に自分なりに一生懸命考えた作文を発表したら、
周りの子に笑われて、それがずっと心に引っかかっていました。
それからというもの、「どう思われるか」が先に浮かんでしまって、言いたいことが言えなくなったんです。
あれはまさに、「自分を出すのは危険」という学習でした。
気づかないうちに、みんな“浮かないように生きる技術”を身につけてしまっているのかもしれません。
思考停止は「ラク」でもあり「しんどい」もの
正直に言うと、「考えなくてもいい生き方」ってラクなんです。
決められたことだけやっていれば怒られないし、波風も立たない。
マニュアル通り、言われたことだけをこなしていれば、それで一日が終わる。
でも──ふとした瞬間、心のどこかで「これって何のためにやってるんだろう?」
そんなモヤモヤが頭をよぎることってありませんか?
僕は会社員時代、朝から晩まで働いて、
帰ってテレビをつけて、疲れた体を横にするだけの生活を繰り返していました。
やるべきことはやっている。家族もいる。
でも…心の奥に、ぽっかりと空いた“穴”のような感覚があったんです。
気づいたあなたは、もう一歩自由に近づいている
この話を読んで、「自分もそうかもしれない」と思ったなら、
それはもう、大きな第一歩です。
多くの人は、その違和感さえ感じないまま、一生を終えてしまいます。
でも、あなたは今ここで気づいた。
そして、この文章を読んでくれているということは、
「もっと自分の人生を、自分の手で動かしたい」と思っているからではないでしょうか。
本当の自由とは、「誰のせいでもない。自分で考えて、自分で選ぶこと」。
僕は、そう思っています。
第2章:大人になっても「正解」に縛られていた僕
会社に入っても、「正解」を探し続けていた
社会人になって、僕は「もう学校じゃないんだから、これからは自由にやっていける」と思っていました。
でも実際は違いました。
会社でもまた、「上司の言うことが正解」「マニュアル通りに動くのが正解」
そんな空気が、ビリビリと伝わってきたんです。
自分なりに工夫してみても、「余計なことはするな」と言われ、
意見を出しても、「それは前例がない」と一蹴される。
結局、ここでも「言われた通りにやるのが正解」と教え込まれてしまうのです。
「いい人」でいようとして、全部自分を押し殺した
僕は、真面目でした。人に迷惑をかけたくなくて、責任感も強かった。
だからこそ、周囲の期待に応えようと、いつも頑張りすぎていました。
無理な残業も引き受け、誰かのミスも自分のせいにして、
どんなに理不尽なことでも「はい、わかりました」と笑っていました。
でも心の中では、毎日叫んでいました。
「俺は何のためにこんなことをしているんだろう…」って。
それでも、“いい人”でいることが正解だと信じていた僕は、
気づけば、自分自身を押し殺すことが当たり前になっていたんです。
本当の引きこもりは、大人になる前に始まっていた
でも正直に言えば──
僕が心を閉ざしたのは、社会に出る前、もっと若い頃からでした。
大学受験に失敗し、就職も決まらなかった20代のはじめ、
「自分は社会から必要とされていない」と感じる出来事が重なりました。
周りは就職していくのに、僕は何も進んでいかない。
その劣等感と孤独に押しつぶされて、僕は部屋に引きこもるようになりました。
カーテンを閉めた薄暗い部屋で、昼夜逆転の生活。
テレビをぼんやりと眺め、本を読んでは、気を紛らわせる日々。
「今日は何曜日だっけ?」
そんなふうに、時間の感覚さえなくなっていきました。
親にも心配をかけ、友人とも疎遠になり、
「自分には価値がない」という思い込みが、心にじわじわと染み込んでいったんです。
でも、もしあの時引きこもっていなければ──
今では思うんです。
あの引きこもりの時間がなければ、
僕はずっと「正解」を追いかけながら、自分を偽って生きていたかもしれない、と。
誰かの期待に応えるためだけの人生。
周囲の目を気にして、本音を隠して過ごす毎日。
あの時間は確かに苦しかった。
でも、その苦しさが“気づき”をくれたとも言えるんです。
「もっと自分らしく生きてもいいんじゃないか?」
そんな問いが、少しずつ心の中で芽生え始めたのは、あの引きこもりの時期でした。
第3章:気づいても、なぜ動けないのか?
「なんかこの社会っておかしくないか?」
そう感じている人は、きっとあなただけじゃありません。
朝の通勤ラッシュに押し込められながら、
職場で何をしても感謝されず、成果を出しても給料は変わらない。
会社では建前がすべてで、本音は誰も語らない。
そんな毎日を繰り返しているうちに、
ふとした瞬間に心の中から「このままでいいのか?」という声が湧き上がる。
でも、その声をかき消すように
「でも仕方ないよな」「みんなやってるし」と自分を納得させてしまう。
気づいてるのに、なぜ動けないのか。
それには、ちゃんと理由があります。
まわりは“ルール通り”に生きている
ほとんどの人が、子どものころから「こうあるべき」「それは非常識」といった
“型”に沿って生きることを無意識に刷り込まれています。
会社では、理不尽でも「上司の言うことは絶対」。
学校では、「目立ちすぎると叩かれる」。
地域でも、「ご近所づきあいはこうするもの」
そうやってみんな、“空気を読んで”“波風立てないように”
“とりあえず正しそうなこと”をやりながら生きています。
そんな中で、「もっとこうすればいいのに」とか
「本当はこれおかしいよね」と声をあげようものなら、
「変な人」扱いされたり、距離を置かれたり、
ときにはあからさまに否定されたりもする。
だから、気づいた人ほど口を閉ざしてしまうんです。
浮く・叩かれる・孤立する…その怖さ
人は、本能的に「仲間はずれ」にされることを恐れます。
これは心理学でいう“社会的排除の恐怖”であり、
進化の歴史の中で身につけてきた“生存本能”なんです。
昔の時代、集団の中で孤立することは“死”に直結していました。
だから僕たちは無意識のうちに、
自分の意見を飲み込み、まわりと同じふりをしてしまう。
気づいていても、行動できない。
それは「勇気がないから」じゃなくて、
「本能レベルで怖い」からなんです。
そして今日も、モヤモヤと向き合えないまま
でも、その怖さに負けて「見ないふり」を続けるほど、
心の奥では不協和音が響き始めます。
・会社の飲み会でつまらない話に無理やり笑う自分
・理不尽なルールに「仕方ない」と従っている自分
・本当はやりたいことがあるのに、「今さら無理だよな」と諦めている自分
そんな毎日を積み重ねるたびに、
「本当の自分」が遠ざかっていくような感覚になっていく。
気づいてる。でも動けない。
そのくり返しが、心にモヤモヤを積もらせていく。
それが現代の“生きづらさ”の正体なのかもしれません。
だからこそ、「気づいた」ことが一歩目
ここまで読んでくれているあなたは、
もしかすると、すでにその“違和感”に気づいている人かもしれません。
そしてそれは、とても大きな一歩です。
なぜなら、ほとんどの人はその違和感すら感じないまま、
“正しそうに見える人生”を歩いて、終えてしまうからです。
だからまずは、自分を責める必要なんてありません。
「気づいた」だけでも、すごいことなんです。
そして、気づきは、必ず“次の扉”を開く鍵になります。
その鍵をどう使うかは、あなた次第です。
次の章では、僕がたどり着いた「自由とは何か?」という問いについて、
一緒に深く考えていけたらと思います。
第4章:本当の自由とは何か?
「自由になりたい」──そう思ったこと、ありませんか?
でも改めて考えると、自由って何なのでしょうか。
好きな時間に起きて、好きなことをして、誰にも縛られない。
それが自由だとイメージする人も多いかもしれません。
でも僕は、「何でもしていいこと」が自由じゃないと思うんです。
自由とは、「選べること」
たとえば、朝5時に起きて仕事に行く人がいたとします。
「それ、全然自由じゃないじゃん」って思うかもしれません。
でもその人が、自分の意思でその生活を選んでいるのなら、
それは紛れもなく“自由な生き方”なんです。
逆に、昼まで寝ていて誰にも文句を言われない生活をしていても、
心のどこかで「本当はこんなんじゃダメだよな」と感じているなら、
それは不自由かもしれません。
本当の自由とは、自分の内側から湧いてくる“これがしたい”に従って生きること。
外側の声ではなく、内側の声に正直でいられること。
それが、僕の思う自由です。
創る側にまわるということ
そしてもうひとつ、大事にしているのが、
「与えられる側から、創る側にまわること」です。
現代は、スマホを開けば答えが出てくる時代。
「おすすめ」はアルゴリズムが決めてくれて、
「流行り」はSNSが教えてくれる。
でもその中にずっといると、
いつの間にか「自分で選ぶ力」が弱くなっていくんです。
気づけば、“誰かが選んだもの”の中から、
「まぁ、これでいいか」と決めるのが当たり前になってしまう。
本当の自由って、自分で問いを立てて、自分で答えを出すこと。
与えられる情報じゃなくて、
自分の視点で世界を見て、何かを創っていくこと。
それが、自由の本質だと僕は思います。
怖さの先にある「実感」
もちろん、自由には“怖さ”もつきまといます。
誰のせいにもできない。
何かあっても、自分の選択として受け止めなければならない。
でもその分、手に入るものもあるんです。
それは、「自分の人生を生きている」という実感です。
自分で決めて、自分で動いて、自分で責任を取る。
たとえうまくいかなくても、そこには誇りがあります。
誰かと比べる必要もない。
自分が納得できる選択をしながら、人生を歩いていく。
その姿こそ、自由であり、強さでもあると僕は思います。
第5章:僕が見つけた、抜け出す方法
僕がここから抜け出すきっかけになったのは、
ほんの小さな「発信」でした。
誰にも見せるつもりのなかったブログ。
ふとつぶやいたSNS。
誰かのためじゃなくて、自分の気持ちを言葉にするためだけのもの。
でも、それが少しずつ「誰か」に届いていきました。
「読んで元気が出ました」「同じ気持ちです」──そんな声が返ってきて、
僕の中の“生きる意味”が、少しずつ動き出したんです。
いつも話しているように、アフィリエイトや情報発信は、
僕にとって「収入」よりも先に、「自分を取り戻す手段」でした。
だから今回は、技術的なことよりも、
「自分の声を言葉にしたこと」が、僕を救った。
その一点だけ、伝えさせてください。
まとめ
もしかすると、僕たちが受けてきた教育や社会の常識は、
「思考を止める訓練」だったのかもしれません。
正解を探すクセ。
空気を読んで本音を隠すこと。
言われた通りに動いていれば安全だと信じてきた日々。
でも、心のどこかで「これって本当に正しいの?」と感じていたなら、
それはあなたの中にいる“本当の自分”からのサインです。
その声に気づいたなら、もう一歩踏み出してみてください。
大きなことをしなくていい。
毎日5分だけでも、自分の気持ちを言葉にしてみる。
ノートでも、スマホのメモでも、ブログやSNSでもかまいません。
あなたの中にある物語は、誰かの勇気になります。
そして、あなた自身の癒しにも、希望にもなります。
自由に生きることは、
「誰のせいでもなく、自分の人生を選んでいくこと」。
それはときに怖いけれど、
だからこそ、本当に生きている実感がそこにあると、僕は思っています。
僕はこれからも、自分の言葉で、気づいたことを伝えていきます。
そしてもし、あなたの中でも何か小さな灯がともったなら──
どうかそれを、自分のペースで誰かに伝えてみてください。
その瞬間から、あなたの人生はきっと、動き出します。
PS.読者から面白いと評判の記事だけ集めました。
→おすすめ記事まとめページ
PPS.実はパソコンを使えば借金を返すことなんて簡単な事を知りました。
もし僕が3500万という膨大な借金を抱え死にかけた所から、借金を完済した人生を同じように歩んでみたいと思ってくれたら、これを読んでほしいです。
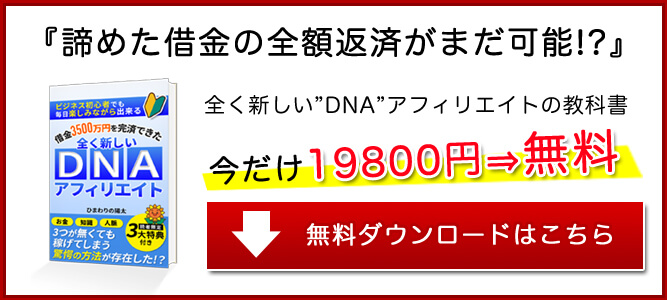
(↑ プレゼント付きなので良かったらどうぞ!)
※ いつでもブロック出来ます
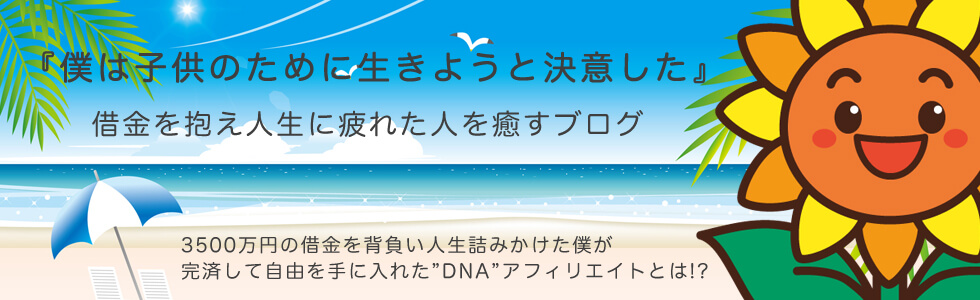


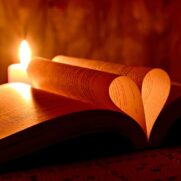





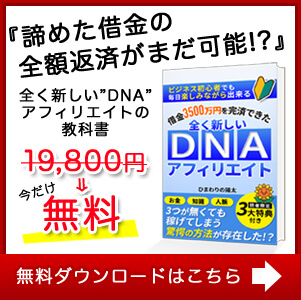
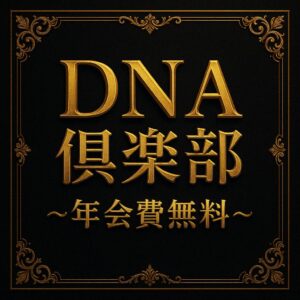

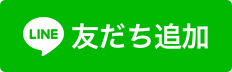

この記事へのコメントはありません。